講師: 斉藤 博昭 氏 (全57回生)
日時: 2019年5月11日 (土) 14時~16時
場所: 湘南高校歴史館スタジオ
新緑の匂い立つ心地よい五月晴れの日に、令和になって初となる第77回湘友会セミナーが開催された。講師は出版社などの勤務を経たのち、1997年から現在に至るまで、フリーの映画専門ライター・ジャーナリストとして活躍する全57回生の斉藤博昭さん。20年以上にわたる映画界の取材現場での経験について講演していただいた。



冒頭、2018年度、世界的に大ヒットした映画「ボヘミアン・ラプソディ」の予告動画が歴史館のスクリーンに映し出された。日本では129億円を超える (セミナー開催日現在) 興行収入をあげ、第1位となった映画だ。40名強の聴講者に対して問い掛けたところ、クイーン世代の50代が中心だったこともあり、半数の人が観に行き、2回以上という人も多数。講師もビックリしていたが、「だからこそ興行収入第1位になったのですね」と感想を述べた。
一方、他国と比べると、アメリカでは同映画の興行収入は10位だったにもかかわらず、倍近い240億円の収入を上げたそうだ。また、同映画に限らない全映画の興行収入では、第1位のアメリカが約1兆3,200億円、第2位の中国が約9,900億円のところ、第3位ながら日本では約2,200億円と大きく差がある。人口に対する映画人口 (映画を見た人数) の比率の比較では、アメリカは3.39 (13億人/3.84億人)、中国でも1.23 (17.16億人/13,95億人)、お隣の韓国では4.30 (2.19億人/0.51億人)。日本は1.34 (1.69億人/1.26億人)。
経済規模は世界第2位になりながらも、内陸部では豊かになりきれていない中国に対してはやや上回ってはいても、アメリカや韓国に比べると日本人は映画館に足を運んでいないということだ。だからこそ、斉藤さんは「自分の仕事を通じて、一人でも多くの人が映画館に足を運んでくれたら嬉しい、また、そうなるように頑張っている」と言う (カッコいい…)。
それにしても、アメリカでは生まれたばかりの赤ん坊も含めた一人当たり平均で年3回以上、韓国では4回以上も、映画館に足を運ぶなんて!!



斉藤さんは“ジャーナリスト”という名称に少々照れくささがあるようだが、かつて海外へ取材に出るようになった折、入管で職業を聞かれ、仕事内容を話したところ、「それは映画ジャーナリストだ」と言われたそうである。
仕事は、国内外で映画関係の取材に行き、雑誌、映画サイトなど、さまざまな媒体に寄稿すること。依頼元は各媒体のほか、映画の配給会社であることも。
ここで、斉藤さんと普段からお付き合いがある、映画配給会社ギャガ株式会社 宣伝部長の中山佳波さん
斉藤さんは、「自分は映画に関わって仕事をさせてもらっているが、映画の製作を行っているわけではないというコンプレックスをどこかに抱えている。でも、今の中山さんの話を聞いて、とても勇気をもらえた」とコメント。
世界中の著名なスターや映画監督たちを相手に、普通の人には経験できない数々の仕事をこなしてきているのにコンプレックスなんて…、高校時代から控えめなところのあった、謙虚な斉藤さんらしい。
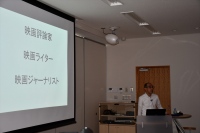


話は少し変わって、湘南高校時代に遡っての映画との関わりについて。
’70年代の頃と思われる藤沢銀座、そこにあった映画館のオデヲン座の写真が映し出されると、聴講席から思わず「おぉ~」「懐かしい!」と声が上がった。皆、歳の頃がバレバレである。斉藤さんは親戚の商売の関係で優待券等がもらえたので、オデヲン座の映画はほとんど見ていたらしい。
また、東京・銀座の映画館に行った時のこと。たまたま隣合わせた妙齢の女性に「映画が好きか」と問われ、「好きです」と答えると、映画の優待券を送ってあげるからと住所を聞かれたそうである。今なら警察に通報されそうな行為だ。けど、後日本当に券が送られてきたとのこと。
ここで高校時代こんなルックスだったという斉藤さんの写真が映し出されると、聴講席から再度、声が上がった。アイドルのようなルックスに対してだったのか、ビフォー・アフターに対してだったのかは別にして、当時、声を掛けたくなるのもわかるような気がした。その女性は、映画ジャーナリストだったそうだが、自分が仕事にしている映画が大好きだという可愛い高校生の男の子が隣にいたら、チケットの1枚や2枚、贈りたくもなるだろう。図らずも、同じ映画ジャーナリストの道に進むことになった斉藤さんは、その後、彼女を探したが、今のところ再会は果たせていないそうだ。ただ、とても運命的なものを感じると言う。映画ジャーナリストという仕事は、神様が斉藤さんに引き合わせた天職なのかもしれない。


映画取材は基本的に、公開に合わせて行われるキャストや監督へのインタビューが多く、インタビューは「単独」「合同」「会見」と、さまざま。斉藤さんは洋画を主に取材対象としているので、世界を飛び回っている。英語が共通語になり、ITが進んできた昨今では、SkypeやFaceTime、電話などでの取材もあるらしい。また製作中の取材 (現場やスタジオ訪問)、映画祭・映画賞の取材もある。
ここで、スクリーンには映画「ソーシャル・ネットワーク」で、Facebookのマーク・ザッカーバーグを演じたジェシー・アイゼンバーグに“単独”で取材している様子の写真が…。通常は肖像権の関係でそういう撮影は許されないらしいので、貴重な1枚だ。他にも、合同取材の様子、トロント国際映画祭でのレディ・ガガ主演「アリー/スター誕生」の記者会見風景など、次から次へと映されていく。
そのような取材を元に記事は書かれるのだが、欧米の俳優や監督の記事は比較的自由に書けるものの、日本では取材対象側のチェックが必ずと言っていいほど入り、あれこれ注文がつくそうだ。とても面倒臭い…、とは言っていないが、斉藤さんの顔にはそう書いてあった……ような気がする。
そのようなチェックのほとんどは事務所やマネジャーらが行うらしいが、元シブがき隊の“モックン”こと本木雅弘さんは、自分の言葉に責任を持って自らきちんと目を通し、手書きで取材者への労いの言葉や要望を丁寧に書いて戻してくれる、とても出来た方だそうだ。スクリーンには、モックン直筆のコメントが書かれた原稿が。 (モックンって、達筆なんだ…)
一方、比較的自由だという欧米でも、昔、ニコラス・ケイジの“かつら”疑惑の記事を掲載した雑誌は、その後、取材を許されなくなったなんてこともあったらしい。自由には、それなりのリスクもあるということなのだろう。
製作現場取材については、メキシコシティの宮殿前広場での「007」撮影風景や、アニメ・CG映画で有名なピクサー本社の様子がスライドで紹介された。
映画祭の取材も行っていて、マイナーな映画祭だが、コロンビアのカルタヘナ国際映画祭には審査員として参加したそうだ。なんてグローバルな! さらに、その時には是枝裕和監督の「そして父になる」が受賞したものの、同映画の関係者が誰も出席していなかったため、同じ日本人だというだけで、斉藤さんが代わりに登壇して受賞したというエピソードも。
その他、「ハリー・ポッター」シリーズのような何作にもわたる映画では、当然ながら取材も長い期間、何回となく行うことになり、ハリー・ポッターの主役3人の成長をずっと見てきたそうだ。第1作の幼い頃、エマ・ワトソンは、ブラッド・ピットに憧れていて、ルパート・グリントはアイスクリーム屋になりたかったらしい。斉藤さんは、ずっと見てきた3人だから、やっぱり応援したくなるし、これからも活躍してほしいと言う。もちろん皆、立派に成長している。ただダニエル・ラドクリフは、あまりにポッター役がはまってしまい、その印象が強く残って苦労しているので、頑張ってほしいと願っているそうだ (やさしい…)。




聴講者の手元には、斉藤さんが取材してきた俳優や映画監督たちのリストが配られていて、国内外合せて177人もの名前がずらりと並んでいた。それも、認知度が高く印象的だった人のみを記載したもので、取材したけれど記載していない人も多数いるとのこと。さすが、20年以上のキャリアはダテじゃない。そんな中から、取材を通して知った彼らの素顔や仕事への情熱が語られたが、これはとても全ては書ききれない。少しだけ披露すると……。
ヒュー・ジャックマンは、とても紳士。真夏の撮影現場、自分は暑苦しい黒づくめの衣装なのに、女優に日傘をさしてあげるような、しかもそれが自然にできる人らしい。スクリーンには、斉藤さんと一緒に写ったヒュー・ジャックマンの写真が。このマスクで、そんなに優しくされたら、誰でも落ちてしまうのではないだろうか…。
また、ドウェイン・ジョンソンは世界一いい人だと言う。それくらい誠実に、インタビューに対して答えてくれる人だそう。一方、ニコール・キッドマンはすごく厳しく怖い人で、取材する時には緊張するとのこと。自分の前に取材に入っていた女性インタビュアーが、泣きながら部屋を出てきたこともあるとか。ハリソン・フォードは元大工で、俳優という仕事は単なる仕事と割り切ってやっているらしい。え、あの名優が!? である。それであの名演なのだから、相当、才能があるのだろう。日本人では、北川景子を、まだブレイクする前に取材したそうだが、気が強く、野心家の一面を見せていた、と。きっと売れるだろうなと思ったそうだが、その通り、今や売れっ子女優だ。




欧米では、政治、宗教、社会問題などについて、正面から捉えた映画が多数生まれているが、日本の映画界はそれが苦手だと斉藤さんは言う。昔は、松本清張の「砂の器」など、そういう類の映画が結構あったのでは?とも思ったが、「砂の器」は背景にハンセン病問題が織り込まれてはいても、あくまで推理映画。確かに、そうだ。斉藤さんはそれが残念だが、最近は「Fukushima 50」「僕はイエス様が嫌い」といった映画が出てきて、期待していると言う。
次に、高校時代の同級生から事前に募った“自分の大好きな映画、人生を変えた映画”を披露。これも全ては書けないが、チェコ在住の古郡 徹さんはチェコ映画の「黄金のウナギ」、ダンス教室を主宰している山下尚美さん (旧姓:重永) は「ロミオとジュリエット」、航空自衛隊の丸山真人さんは「愛と青春の旅だち」「トップガン」、元タカラジェンヌで女優・演出家の登坂倫子さんは「チャーリング・クロス街84番地」。本人たちを知っている聴講席の多くの同級生は、「ああ、そうだろうな!」と思っただろう。丸山さんに至っては特に分かりやすすぎる (笑)。それくらい、映画というものはその人を映すし、人の心に残る、と改めて思う。


フリーランスの仕事は、組織には縛られないが、安定性という点で厳しい面もある。そんな中で斉藤さんは、毎回、その仕事が自分に来たのは、意味があって来たものと思って取り組むそうだ。そうやって誠実に仕事をこなしてきたからこそ、20年以上という長い年月、一線で働き続けていられるのだろう。同窓生として誇らしい。
また、斉藤さんはジョディ・フォスターの話をした。彼女は映画「羊たちの沈黙」の仕事の打診があったとき、引き受けるかどうか迷ったそうである。直前の映画「告発の行方」で、アカデミー賞の主演女優賞を受賞するなど、十分な評価を受けたところで、あえて猟奇殺人を描いたリスキーな仕事を引き受ける必要はないとの周囲の猛反対があったからだ。しかし、彼女は自分の中の本能による「引き受けるべきだ」という確信によって引き受けた。結果、同映画はアカデミー賞で主要5部門を受賞し、彼女は2度目の主演女優賞を受賞することとなった。
斉藤さんは、自分もフリーになるのは不安だったけれど、本能に従った。そして今があると言う。だから、結構、人間の本能って信じていいんじゃないか、信じて冒険してもいいんじゃないか、と。それが、今後何かを目指す人へのメッセージだと言う。本講演の聴講者は、ほとんどが50歳を過ぎたシニアだったが、数名の現役高校生も参加してくれた。斉藤さんのメッセージが、もっと若い世代に届いてくれたらと思う。楽しみだ。
斉藤さんへ。講演の半分も報告できていないのがもどかしいけれど、いい講演だった。ありがとう!
とてもまた映画が観たくなったよ。もちろん、映画館に足を運んでね。



<追記>
セミナーの後、斉藤さんは在校生から「将来、映画に関わる仕事に興味があるのですが、どうすればいいでしょう?」という質問を受けたそうだ。全71回生の中山さんと一緒にいくつかの選択肢をアドバイスして、「若い世代に何かを届けるという目的を少しだけ達成できました。ありがとうございます」と斉藤さん。最後まで、謙虚な彼らしい。今回の講演が、若い世代に何かを伝えたなら、この講演を企画した一員としてこれ以上の喜びはない。斉藤さんに心から感謝したい。